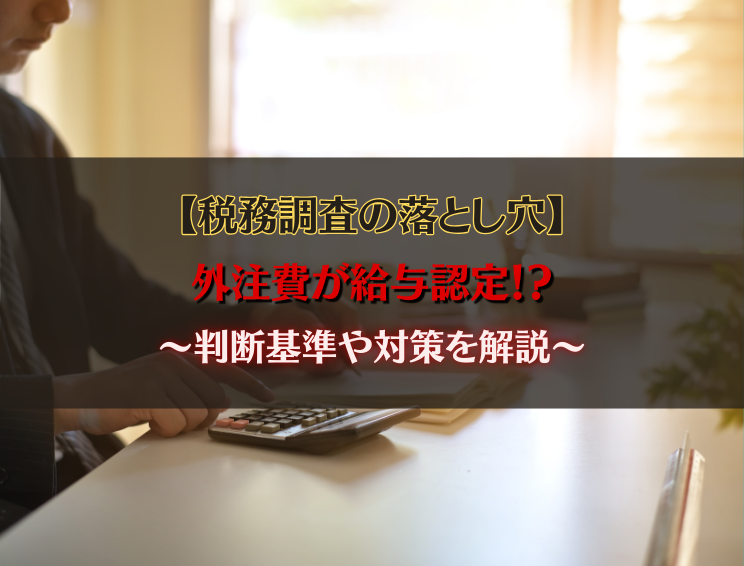
【税務調査の落とし穴】外注費が給与認定!?デメリットと対策について
この記事をご覧の方は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 「外注費と給与ってどう違うの?」
- 「給与認定された外注費のデメリットって何?」
結論から言いますと、外注費が給与認定されると「源泉徴収」が必要になり、存在を忘れていると「不納付加算税」を課される可能性があります。
本記事では、以下の内容を解説していきます。
- そもそも外注費とは?「給与」との違いを解説
- 給与か外注費かの判断基準
- 外注費を給与認定される場合のリスク・デメリット
自分にも源泉徴収義務が発生しているかもしれないという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
そもそも外注費とは?「給与」との違いを解説
外注費とは、一般的に「社外の人員に作業させた際に発生する対価」を指します。
そのため、会社内で雇用している人員に支払うものではなく、雇用契約を結んでいる人員に支払うものは「給与」として扱われます。
下表で外注費と給与の違いを簡単に事例一覧にしてみました。
項目 | 給与 | 外注費 |
対象者 | 従業員 社員 | フリーランス 個人事業主 下請の会社 |
支払いの性質 | 労働に対する報酬 | サービスや業務の成果物に対する報酬 |
契約形態 | 雇用契約 | 業務委託契約 請負契約 |
税務処理 | 給与所得として処理 源泉徴収あり | 必要に応じて源泉徴収あり (所得税、住民税等) |
社会保険 | 雇用保険 健康保険 厚生年金保険の適用あり | 通常は適用なし (個別の契約による) |
必要な書類 | 給与支払報告書 源泉徴収票 | 支払調書 契約書(場合による) |
費用処理 | 人件費として処理 | 外注費として処理 |
その他の注意点 | 労働基準法等の適用 | 業務委託の範囲と責任の明確化が必要 |
給与と外注費の大きな違いは、以下に挙げる3つです。
- 雇用関係の有無
- 福利厚生の有無
- 請求書発行の主体
こちらについて詳しく紹介します。
①雇用関係の有無
結論から言いますと、外注費を支払う相手とは雇用関係にありません。
雇用契約とは主従関係であり、雇い主の「下」にいる相手に支払うのが「給与」です。
一方、外注費での取引を行うのは「対等の関係」です。
発注者と受注者ということで、上下関係があるように見えますが、受注者には「拒否権」もあるので、主従関係とは違います。
つまり、発注者の依頼には強制力はなく、雇用関係の場合は指示された作業を常に受諾しなければならないということです。
もちろん、雇用関係でも意見がぶつかることはありますが、最終的には指示に従わなければならない関係なのです。
②福利厚生の有無
外注費で仕事を請け負う場合、発注者には受注者に対する福利厚生を与える義務はありません。
保険や年金関係は、全て受注者本人の責任によって対応しなければならないのです。
一方、雇用関係にある場合、雇用主には従業員に対し福利厚生を提供する義務があります。
厚生労働省では、雇用保険制度を以下のように定めています。
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。 |
(引用:厚生労働省 雇用保険制度)
つまり、雇用保険は「仕事に必要な教育のための資金」や「失業時の救済資金」のための制度です。
さらに社会保険加入も雇用関係の福利厚生として指定されており、社会保険加入には厚生年金も付帯します。
社会保険を取りまとめている「一般財団法人社会保険協会」が、なぜ社会保険というシステムを重要視しているかの説明を見てみましょう。
当協会は、健康保険、厚生年金保険、船員保険及び国民年金の被保険者等並びに社会保険制度に携わる者(携わった者を含む。)の福祉を増進し、社会保険事業の普及発展のために必要な事業を行い、もって社会保険制度の円滑な運営と健全な発展に寄与することを目的としています。 |
一般的には健康保険は「国民健康保険」、年金制度は「国民年金」という国や地方自治体が管理するものです。
しかし、社会保険は民間が管理しているため、透明性という面で有利な条件を得られるでしょう。
③請求書発行の主体
一般的な雇用形態であれば、報酬の支払いは「給与」です。
この給与には請求書を作成する必要はありません。
雇用契約を結ぶ際に報酬額を取り決め、明記しているため、従業員は支払日に指定された方法で給与を受け取ることができます。
一方、外注費の支払いは、一般的に請求書のやり取りを求められます。
しかし、このやり取りは義務ではなく、相互補助のためのものであることを覚えておきましょう。
その上で、請求書のやり取りをする際の主体は「請求書発行者」であり「受注者」になるのです。
業務委託契約を結ぶ際も、報酬や作業場所等の明記が必要です。
受注者にとっては取引の大きさを左右するものなので、雇用契約以上に重要な意味を持ちます。
つまり、業務委託契約書には作業報酬についても明確に記載されているのです。
当然、金額だけではなく締日や支払い期日についても仔細が明記されているため、発注者はこの契約書の通りに報酬を支払うことができます。ここに請求書の存在は必要ありません。
ただし、請求書があることで受注者が行った作業と報酬額の根拠が示せるのです。
また、発注者にも支払い根拠ができるため、税務調査で指摘される原因を取り去れるということを覚えておきましょう。
給与か外注費かの判断基準
報酬の支払いが「給与」か「外注費」かの判断はどこでするのでしょうか。
先にも明記した通り、請求書の発行は義務ではありません。
もし、請求書を介さずに報酬の支払いを履行されたとしたら、両者の差は目に見えないため、判断に困ることでしょう。
実際にどういった基準で給与と外注費が判断されるのか、基準を解説します。
①役務の代替について
単純な判断の仕方ですが、業務を履行するのが「会社内」の人員であれば「給与」での支払いが基本です。
反対に、履行者が「会社外」の人員であれば「外注費」での支払いが一般的でしょう。
これは、あくまでも「社内」という括りが重要です。
受注者が発注者の子会社だった場合でも、社内には該当しません。
建設業で例を挙げると、大規模な建設会社が、子会社であるハウスメーカーに分譲住宅建設を依頼したとします。
この場合、発注元の建設会社も専門的な知識は持っていますが、実務に携わるのはハウスメーカーです。
グループ企業ではありますが、報酬を計上する際の会計科目は「外注費」での記載になるでしょう。
つまり、受注者が完全な別事業体でなければ外注費にならないというわけではないのです。
②時間的な拘束について
雇用契約には「作業に従事する時間」について明記されます。
俗に「コアタイム」と言われている働き方で、専従時間の設定があり、就業時間内は作業に従事しなければなりません。
しかし、業務委託契約の場合、作業に従事する時間は発注者に指定されないのが特徴です。
利用する道具や方法にも限定条件はほぼなく、依頼内容を正しく成果として提示できれば問題にはなりません。
TPOを弁えた範囲であれば、ある程度自由にできるのが業務委託です。
③事業者の指揮監督について
作業をする際、その現場を監督する人員がどこにあるかによっても報酬形態が変わります。
これは①にも共通することですが、監督者の所属元によって、給与か外注費なのかは変化します。
例えば、発注者から監督者が派遣された場合、たとえ遂行方法が受注者のやり方を遵守されていたとしても、発注者が監督していると判断されます。
ここで発生する報酬は「給与」として判断されやすくなるでしょう。
反対に、発注者からは何も指示がなく、受注者が全ての責任を背負っているのであれば、報酬は「外注費」と判断できます。
本来であれば、監督者の本当の所属先だけではなく、実際に監督していたのは誰かが重要になりますが、その現場を目にしているわけではなく国税庁職員には、申告内容からしか判断できないのです。
④請求について
給与で報酬を受け取る対象は、成果の受け渡しが完了していなくても報酬を受け取る権利を持っています。
しかし、外注費で受け取る場合は、成果を発注者に引き渡さなければ報酬を受け取ることは難しいでしょう。
絶対に受け取れないというわけではなく、発注者が成果を受け取る前に報酬を支払うとは限らないということです。
また、成果の引き渡し前に不可抗力によって受け渡しができなかったなら、外注費は支払われません。
しかし、給与の場合はこの限りではなく、たとえ成果がなかったとしても、給与報酬は支払い期限までに必ず支払われます。
⑤材料や用具の支給について
事業運営のための材料や用具は、一般的に事業者自ら用意するものです。
給与報酬の場合、会社が用意し、業務を遂行します。
外注費であれば受注者が用意するのが一般的ですが、発注者が貸与することもあるでしょう。
わかりやすく説明すると「材料や用具が用意されれば給与、自分で用意すれば外注費」ということです。
外注費を給与認定される場合のリスク・デメリット
外注費で報酬を支払っているにも関わらず、給与認定されることはあります。
これには、以下に挙げるようなリスクやデメリットがあると覚えておきましょう。
- 源泉所得税の追加徴税
- 消費税の増加
- 信頼やイメージの低下
これらについて解説します。
①源泉所得税の追加徴税
外注費は「源泉徴収義務なし・課税仕入れあり」という考え方があります。
しかし、給与認定されてしまうと、債務者は「源泉徴収あり・課税仕入れなし」という考え方に変わってしまい、事業者側で源泉徴収をしなくてはいけません。
この考え方は、納税者と課税者という立場の違いに現れます。
②消費税の増加
外注費と給与では、消費税の取り扱い方に違いがあります。
「消費税法基本通達1-1-1」に以下のように記載されているので、確認してみましょう。
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。 (1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。 (2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。 (3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。 (4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 |
(引用:国税庁 消費税法基本通達1-1-1 個人事業者と給与所得者の区分)
これらをもっとわかりやすくすると「給与認定されることで約22万円分の仕入税額控除が受けられなくなり、その分の消費税を納めなければならない」ということです。
③信頼やイメージの低下
外注費が給与認定されてしまっただけでは、決して信頼失墜やイメージダウンにはなりません。
しかし、給与認定によって源泉徴収義務紙が発生しているにも関わらず、源泉徴収を忘れ納税義務を全うできなかった場合、不納付加算税を課される可能性があるのです。
これは明らかな信頼失墜やイメージダウンにつながる理由です。
外注費を認めてもらうためのポイント
給与認定によって生じるデメリットを避けるには、以下に挙げるポイントを押さえておきましょう。
- 業務委託契約書などの書類を用意する
- 業務実態を整える
- 税理士に相談する
それぞれを簡単に解説します。
①業務委託契約書などの書類を用意する
外注費として申告を認めさせるには、業務委託契約書や請負契約書の存在が重要です。
決して雇用関係にないという事実を提示できれば、給与認定はされません。
②業務実態を整える
給与と外注費の判断は「雇用形態」か「業務委託契約」なのかがポイントです。
また、その事業実態も重要なので、国税庁では以下の事項を判断材料として明記しています。
(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。 (2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。 (3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。 (4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。 (5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。 |
(引用:国税庁 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達))
つまりは以下のポイントが重要だということです。
- 請負契約か
- 誰でも業務代替できるか
- 独断で業務遂行できるか
- 成果の授受をもって報酬を受けるか
- 道具や資材を自ら準備するか
これらに1つでも「NO」があれば給与認定されるでしょう。
③税理士に相談する
外注費を給与認定されたくないなら、契約時から税理士がそばにいる状況を作るべきです。
税理士がいれば、仕入れの際もより有利な原価での仕入れができるように、情報を集めてもらえるでしょう。
万が一、給与認定されてしまった場合も、すぐに源泉徴収対応に着手してくれることでしょう。
税理士をお探しなら「TRUSTマーケット」
まとめ
外注費が給与認定されたとしても、多くの事業者がどんな対応をすべきか理解しているわけではありません。
知らぬ間に税務調査の対象に選ばれてしまい、最悪の場合追徴課税を受ける可能性もあるのです。
もし、源泉徴収義務者の通知を受けた場合は、どの期間で源泉徴収しなければならないかを確認しましょう。
どうすれば確認できるかがわからなければ、できるだけ早く税理士に相談してください。

